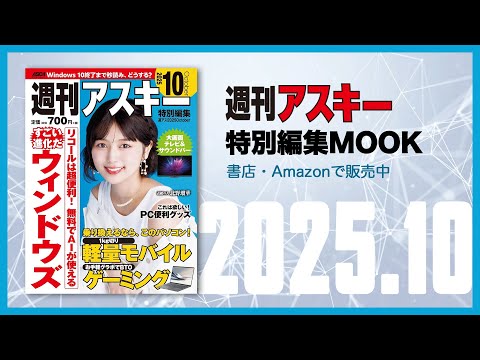マイクロソフト トレンド
0post
2025.11.23 01:00
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
記憶體產業疑慮Q&A
2025/11/21
💎訊息內容
在全球記憶體類股出現較大幅度修正後,我們整理並回覆近期投資人所關注的疑慮。
💎評論及分析
1. Q: 長鑫存儲(CXMT)是否可能重新擴產DDR4?
A: CXMT目前僅保留約20kwpm的DDR4產能供GigaDevice代工使用,而其2026年超過90%的產能將轉向G4製程。根據我們了解,CXMT並未在G4製程規劃DDR4產品,即便此刻重新啟動DDR4開發,自設計到量產仍需約一年。考量2027年DDR4約80%以上位元需求將來自Consumer應用,我們認為CXMT沒有重新擴產DDR4的動機與經濟誘因。
2. Q: CXMT是否有計畫擴產DDR5/LPDDR5,若擴產是否可能導致供需反轉?
A: CXMT的總投片預計由4Q25的280K僅小幅提升至4Q26的300K,投片主要用於生產DDR5/LPDDR5,屬於既有規劃,並非近期新增擴產。目前造成DRAM供不應求的核心為Server端需求強勁。然而CXMT現階段僅能量產DDR5 16Gb,其可支援的RDIMM(伺服器用記憶體)最高容量僅64GB,但2026年主流需求將轉向96GB與128GB,因此CXMT對於緩解Server DRAM供需吃緊的實質幫助有限。
3. Q: SK Hynix是否計畫於2026年將1cnm製程投片量擴大至當前的8倍?
A: 我們的供應鏈調查顯示,SK Hynix的1cnm製程投片量將由目前約20k提升至4Q26的100k,擴產幅度約5倍,主要用於生產DDR5 16Gb/24Gb、LPDDR5X 24Gb與HBM4e。然而,1cnm為SK Hynix現階段已量產的最先進製程,持續Ramp up屬既有規劃,其2026年整體DRAM投片量仍維持在約600k水位。
4. Q: Samsung是否計畫於2026年底將1cnm製程投片量擴大至200k,若情況屬實,是否可能導致DDR5供需反轉?
A: 我們的供應鏈調查顯示,Samsung的1cnm製程投片量預計於4Q26由原先規劃的140k提高至180k。然而目前Samsung並無1cnm DDR5/LPDDR5產品的明確送樣與量產時程,此次擴大1cnm投片主要用於HBM4生產。由於更多1cnm產能被HBM4所排擠,反而將使DDR5/LPDDR5供給進一步趨緊。
5. Q: 近期現貨價漲勢趨緩,是否意味後續合約價漲幅亦有限?
A: 我們在通路端了解到,當前原廠普遍惜售,現貨顆粒報價稀少,即使賣方願意報價,其價格也偏高,甚至高於調研機構統計的現貨最高價。由於現貨與合約價差距過大,買方難以追價,成交量因而極低。基於上述狀況,我們認為現貨價目前對於研判未來合約價的參考意義相對有限。
另一方面,在一個完整的上行循環中,現貨價往往會出現多段上漲。我們研判,隨下游客戶庫存去化至一定水位,加上中國政府預計於明年初公布新一年度預算,相關採購需求可望回溫,農曆新年期間現貨價可能迎來新一波漲勢。
6. Q: 為何當前上下游廠商對於DRAM/NAND Flash漲幅與漲價持續時間的看法出現明顯分歧?
A: 部分下游PC OEM與IPC廠商認為本輪DRAM與NAND Flash供應短缺屬暫時性現象,預期後續價格將逐漸鬆動,並認為2026年PC/NB/IPC出貨受記憶體漲價的影響有限。相較之下,ODM廠商對2026年PC/NB出貨展望則較為保守。
我們在2025/11/17發布的產業報告《通用型伺服器採購潮點燃記憶體超級週期》中指出:來自通用型伺服器需求上檔加速了價格推升以及缺貨預期。根據凱基供應鏈調查,美系CSP對於明年通用型伺服器採購大幅優於預期和歷史均值,其中以Microsoft最為積極,預期2026年美系CSP通用型伺服器出貨量可望挑戰年增50%。
我們認為,上下游觀點分歧的核心原因在於:本次記憶體需求上行並非由PC/NB/IPC所帶動,而是由Server端主導;因此各應用端在判斷後續需求時自然產生落差。
7. Q: 若DRAM/NAND Flash價格過高,是否可能反過來壓抑需求,進而導致供需反轉、價格崩盤?
A: 過去記憶體漲價通常難以維持多季,主因需求集中在手機與PC,而記憶體約占手機/PC BOM Cost的10-20%,品牌廠與OEM在承受成本壓力後不得不調漲終端售價,進而壓抑需求。
然而本輪上行循環的驅動因素由Server主導,美系CSP的採購行為對價格的敏感度遠低於終端消費者,因此需求彈性較低。我們認為,本次需求結構明顯不同於過往手機/PC主導的循環,記憶體價格上行有望維持更長時間,而非快速反轉或崩盤。
8. Q: 當前記憶體類股評價是否仍有進一步上修空間?
A: 我們在2025/11/17發布的產業報告《通用型伺服器採購潮點燃記憶體超級週期》中指出:2026年全年記憶體將維持供不應求,其中3Q26為最為吃緊的季度,DRAM/NAND Flash供需比分別為90.17%/90.12%。此外,我們在2025/11/03的南亞科報告《別讓歷史經驗限制了你對合約價漲幅的想像》中亦強調,2026年全年DDR4將維持約28%的供需缺口。
我們當時預估4Q25-2Q26 DDR4 8Gb合約價將上升至7.5/10.0/12.0美金,2H26則維持在12.0美金。然而隨著DDR5顆粒價格持續大幅上漲,Consumer端升級DDR5的意願放緩,DDR4將因此受益而具備進一步上漲的可能。我們目前認為,南亞科1Q26 DDR4 8Gb季合約價有望季增65%以上,且DDR5將於2H26持續上漲,則DDR4顆粒亦具備同步續漲的空間。
若DDR4顆粒於2H26續漲,則南亞科、華邦電等相關公司之ASP與EPS均將進一步上修,股價亦有望在獲利預期上調的驅動下進一步Rerate。 November 11, 2025
2RP
\✨Windows は今日で 40 周年!✨/
今日は Microsoft Windows 1.0 がリリースされた日!
1985 年 11 月 20 日に登場した #Windows は、今日で 40 周年を迎えました🎉
40 年の進化を、懐かしい歴代の Windows で振り返りましょう👀 https://t.co/PJb4u0PJl2 November 11, 2025
1RP
個人的に、つい先日 Microsoft が発表した Agent 365 はエンタープライズでやってる人は必須で押さえておいたほうがいいと思っている。
Agent 365 は、要はこれから爆増するエージェントを「社員のように登録してまとめて管理する」するための仕組み。
面白いのは、エージェントの技術スタックも、稼働している場所も問わないこと。
AzureとかCopilot Studioは当然として、外部のSaaS だろうと、OpenAI Agents SDKだろうとClaude Code SDKだろうとLangGraphだろうと何でもいい。
そこにAgent 365 SDKをかぶせてM365の世界でidを振ってやると、Copilotのレジストリに登録されて、その先は権限制御とか監査用のログの取得やら監視やら、あらゆるエージェントを全部同じ仕組みで運用できるようになる。
しかもそのエージェントはWorkIQって仕組みをつかってCopilotのようにm365上のデータにアクセスできるようになる(権限を持っている範囲だけ)。
ユーザー企業としてのメリットは↑の通り、エージェントの爆増に対してガバナンスを利かせやすいし、
エージェント提供側は、ユーザー企業に「Agent 365 に対応してるなら既存の運用に乗せられるか」と考えて使ってもらいやすくなる。
すでに結構なところが対応を表明してるのと、昨日?一昨日?くらいにさっそくGensparkが対応してた気がする。 November 11, 2025
1RP
https://t.co/x6xlWjKeaE
純正のMicrosoftコントローラでも良かったと思うけど、初めて純正じゃないコントローラ買ってみた
まじでドキドキ、エレコム最近新しいゲームパッド発売したらしいし
届くの楽しみだな November 11, 2025
Microsoft Agent Framework (C# ) を見てみよう その15 Durable Agent で長時間ツール呼び出し|Kazuki Ota https://t.co/zSwcaqrGtX #zenn November 11, 2025
我々一般人にとってMicrosoft Excelにおいて
セル結合を行った場合 信仰を持っていても
神の国に死後召されることはできるのかという
宗教的倫理問題が存在する[要出典] November 11, 2025
「Google Brain Tokyo(現Google DeepMind Tokyo)に、昔のアジアに於けるMicrosoft Research Beijingのような存在になってほしかった。あれこそが、現在のフロンティアモデルにおける中国の優位性を生み出した直接的な要因だから」
:残念! https://t.co/PmCb0DSmVe November 11, 2025
長年にわたり、権威ある雑誌『Philosophy&PublicAffairs』は、年間約14本の査読付き論文を掲載していました。
そのため、著名な学者で構成される少人数のボランティアスタッフは、出版社であるワイリーが大幅な増刊号の発行を要求し、一時は60日以内に35本の新規論文の掲載を要求したことを知り、衝撃を受けました。
カリフォルニア大学バークレー校の当時の編集長アンナ・スティルツは、査読プロセスを妥協して質の低い論文を急いで印刷する代わりに、反乱を起こし、最終的には同誌の編集スタッフと理事会全員の大量辞任に至った。
「ワイリーは、もっと論文を発表しなければ、雑誌を長く続けられないと言いました。話し合いは非常に敵対的でした」とスティルツ氏は大量辞任について説明した。「読者に質の高い記事を提供したかったので、厳選していました。」
この反乱は、何世紀にもわたって研究と学問の基盤となってきた、影響力のある学術雑誌界を巻き込む危機の最新例の一つです。
近年、ワイリーをはじめとするビッグファイブと呼ばれる4つの大手学術文献出版社は、論文出版数を前例のないほど大幅に増加させることで、堅調な利益率を生み出してきました。
数年前に中国が世界のリーダーとして台頭したことによる研究のグローバル化、そして学術的成功の生命線である「出版しなければ滅びる」という精神が、学術研究の雪崩を巻き起こしました。
ビッグファイブは、新しい雑誌や特集号の創刊、そして既存の雑誌の充実化を通じて、この状況に対応し、奨励してきました。
科学者たちでさえ、学術出版の多くが暴走し、エルゼビア、シュプリンガー・ネイチャー、テイラー・アンド・フランシス、ワイリー、セージが所有する1万2000誌の多くで品質管理体制が崩壊していることを認めています。
RealClearInvestigationsが報じているように、悪質な論文作成業者が出版の混乱に乗じ、偽データやAI生成テキストを用いた不正論文をますます多く生み出し、科学の世界を汚しています。
出版業界の混乱は、神聖な学術界の外にも影響を及ぼしている。ビッグ5と小規模出版社が研究論文から得る年間120億ドルの収益は、納税者にとっても大きな問題となっている。
この収益の相当部分は、公立大学や連邦政府からの助成金によるもので、これらは研究者の論文をジャーナル購読やインターネット上で無料で読者に公開する対価として出版社に支払われている。
こうした助成金に加え、ジャーナル編集者は通常無償で作業するため、制作コストが低いことから、ビッグ5の利益率は30~40%に達し、昨年はマイクロソフトやアルファベットに匹敵し、アップルを上回った。
「最大の問題は、研究に使われるはずだった納税者のお金が、これらの出版社に流れていることです」と、出版市場の著名な研究者であるオタワ大学のステファニー・ハウスタイン教授は述べています。
「出版は無料であるべきだと言っているのではありませんが、これらの出版社はとんでもない利益を上げています。彼らは納税者から不当に高い値段をつり上げているのです。」
NIH、手数料の抑制に着手
トランプ政権は、論文掲載料の抑制に動いている。国立衛生研究所(NIH)のジェイ・バッタチャリア所長は7月、出版社の論文掲載料(APC)が「不当に高い」と述べた。
論文が「オープンアクセス」、つまり無料で公開されるようになったため、APCは購読料に代わる選択肢としてますます人気が高まっている。
バッタチャリア所長は、納税者保護のため、1月からNIHの資金提供を受けた論文の掲載料に上限価格やその他の制限を設けると述べた。
ビッグファイブは、出版にかかる多くのコストを自社の手数料が公正に反映しているとして、この上限設定に反対している。
テイラー・アンド・フランシスの広報担当者はRCIに対し、「APC(出版手数料)上限設定は、解決するよりも多くの問題を生み出す、無神経な手段です。著者の選択肢を制限し、不平等を悪化させ、出版エコシステムを不安定化させるでしょう」と述べた。
ケンブリッジ大学出版局の報告書によると、一部の批評家は価格上限の先にある「学術出版の根本的な変化」を期待している。
同局は3,000人の研究者、図書館員、そして資金提供者を対象に調査を行い、出版社にとって「驚くべき」結論に達した。
それは、学術界が商業出版よりも低コストの代替手段を構築する一方で、業界は論文の大量出版を減らし、量よりも質に重点を置くべきだというものだ。
「膨大な量の出版物がエコシステムを圧倒する恐れがあります。重要な研究が、低品質なコンテンツやAI生成コンテンツの急増によって失われたり、かき消されたりする危険があります」と、同出版社のマネージングディレクター、マンディ・ヒル氏は10月の報告書に記しています。
学術出版の秘密のソース
商業的な学術出版よりも優れたビジネスモデルを想像するのは難しい。
調査によると、索引付けされた論文の50%以上を占めるビッグファイブの独占状態は、インフレ率を上回る料金引き上げを可能にする市場力をもたらしている。
大学は、コストのかかる悪循環に陥っている。
大学は、平均で年間約1100万ドル、つまり図書館の総予算の約3分の1にまで上昇した料金にしばしば抗議する一方で、研究者に出版ペースを速めるようプレッシャーをかけている。
その結果、ジャーナル、特にビッグファイブのNatureやCellといった料金が最も高い権威あるジャーナルへの掲載枠に対する旺盛な需要が確保されている。
学術出版社は、独占市場に加えて、業界特有の大幅なコスト削減も享受しています。
出版社は様々な運営コストを負担しますが、論文を執筆する研究者、論文を改訂する編集者(編集長への少額の謝礼を除く)、そして基本的な品質管理を行う査読者には報酬を支払っていません。
ドイツのライプツィヒ大学のアレクサンダー・グロスマン氏による2021年の研究によると、論文の出版コストは平均で約400ドルである一方、ジャーナルが徴収する論文処理手数料は平均で1,800ドルとなっている。
「学術界が費用負担の問題に取り組むには、最終的にはいくつかの決断を下さなければならない」と出版学の教授であるグロスマン氏は述べている。
「税金で30~40%の利益率というのは許容できるのだろうか?」
ビッグ5は納税者から搾取しているという主張を否定している。テイラー・アンド・フランシスの広報担当者はRCIに対し、これらの料金は「投稿・査読管理、編集開発、倫理審査・調査、メタデータのタグ付け、索引作成、指標、コンテンツ保存、技術開発など、出版サービス全般をカバーするために必要だ」と述べた。
シュプリンガー・ネイチャーの広報担当者はRCIに対し、論文処理費用は論文出版に伴う費用と同額であると述べた。
「当社が提供するアウトリーチ活動や編集サポート、当社が実施する科学研究のプロモーション、そして当社が維持・投資するインフラはすべて、研究のリーチと影響力を高めるという一つの目標を念頭に置いて行われています」と広報担当者は述べた。
ビッグファイブの成長
学術出版の危機は数十年にわたり続いてきた。
1970年代、ビッグファイブは市場の10%未満を支配し、そのシェアを科学学会や大学出版社と共有していた。
そのシェアは主に図書館へのジャーナル購読を通じて提供されていた。
購読モデルは当初から物議を醸し、議会図書館は購読料の「急激かつ憂慮すべき値上げ」(ほとんどの年で5%から12%の間で推移し、インフレ率をはるかに上回っていた)が「図書館の」コレクションの発展に「悪影響」を与えていると批判した。
大学図書館の予算が停滞し、購読料の高騰に圧迫される中、2000年代初頭、学者や図書館員の反乱によりオープンアクセス運動が勃興しました。
この運動は、出版コストを削減するとともに、数百万ドルもの購読料を支払うことができない大学を抱える発展途上国の、拡大するグローバルな研究コミュニティと論文を自由に共有することを目指しました。
オープンアクセス契約では、大学や研究者は出版論文ごとに1回限りの論文処理料を支払うだけで、インターネットによって可能になった論文は永久に無料で公開されます。
1990年代の二度の統合の波を経て市場シェアをほぼ5倍に拡大したビッグファイブは、バイオメッド・セントラルなどの少数の小規模出版社が最初に導入した新しいオープンアクセスモデルに抵抗しました。
しかし、オープンアクセスが勢いを増すにつれ、シュプリンガーは2008年にバイオメッドを買収しました。
これはビッグファイブがこのモデルを受け入れる最初の一歩となり、ビッグファイブに第二の収入源を与えました。
今日、研究者たちは、世界で出版される論文のほぼ半分を占めるオープンアクセスの成長を、知識の普及における勝利として称賛しています。
しかし、出版コストは削減されるどころか、上昇し続けています。
オタワ大学学術コミュニケーション研究所の共同所長であるハウスティーン氏は、2019年から2023年にかけて主要出版社6社から得た手数料に関する広範な調査で、研究者が2023年にこれらの出版社に支払った論文処理手数料は25億ドルに上り、2019年の3倍に達したことを明らかにした。
ジャーナルのほぼ90%が手数料を値上げしており、その額はインフレ率を上回る場合が多かった。
平均手数料は1論文あたり約2,900ドルで、著名なジャーナルでは最高11,700ドルに達した。
「我々の分析は、APCに莫大な金額が費やされており、この金額がほぼ確実に持続不可能な速度で増加していることを示しています」と共著者のハウスティーン氏は書いている。
出版社が論文数に応じて報酬を受け取る場合、論文の出版数を最大化するインセンティブが生まれ、論文ブームの要因の一つとなっている。
エクセター大学のマーク・ハンソン氏の研究によると、索引付けされた論文の総数は2016年から2022年の間に47%増加し、28億本に達した。
出版数の急増を牽引したのは、オープンアクセス論文に特化した大手出版社MDPIだった。
MDPIは、研究テーマを軸に特集号を組む際の論文掲載料から収益の大部分を得ていた。これは、質より量の危機を象徴するものだ。
特集号では、ゲスト編集者が研究者に論文を依頼することで需要を喚起しており、研究者が準備ができたら論文を投稿するという従来の慣例を覆している。
ハンソン氏の研究によると、投稿から受理までの時間も短縮され、編集者が論文の弱点や不正行為を精査する時間が短縮されている。
また、MDPIは論文の却下率が低いことでも、出版社の中で際立っていた。
「出版社が論文の却下率を下げれば、他の条件が同じであれば、より多くの論文が出版されることになる」とハンソン氏は記している。
「却下率の変化は、質の低い論文の出版が増えることも意味するかもしれない。」
特集号に特化した別の出版社であるヒンダウィの破綻は、出版業界に同社の不正問題の深刻さを知らしめた。
ワイリーは2020年にヒンダウィを2億9800万ドルで買収し、「オープンアクセス出版のイノベーター」と称し、急成長する市場に進出し、論文処理費用を稼ぐ狙いがあった。
しかし3年後、ワイリーはヒンダウィに製紙工場が深く浸透していることを発見し、8000本の疑わしい論文を撤回せざるを得なくなり、ヒンダウィブランドは終焉を迎えた。ヒンダウィは、制御不能な出版業界の象徴として今も生き続けている。
不正なペーパーミル(偽造文書製造業者)の検知
2025年の調査によると、大手5社は現在、不正論文の出版抑制に真剣に取り組んでいると表明している。
不正論文は正規の出版物よりもさらに速いペースで増加している。
昨年230万件の投稿を受けたシュプリンガー・ネイチャーは、AI生成のテキストや画像など、疑わしい論文を出版前に特定し、研究の信頼性を確保するために、技術に数百万ドルを投資し、75人の専門家チームを編成したと広報担当者は述べた。
テイラー・アンド・フランシスは、同社のインテグリティチームが「毎年数千件の不正論文の出版を阻止している」と述べている。
しかし、欠陥のある論文や偽造論文が依然として多数出版されており、ビッグファイブが論文製造業者との戦いにもっと力を入れるべきではないかという疑問が生じている。
例えば、ジャンクサイエンス論文が疑わしいと指摘されてからジャーナルが撤回するまでには何年もかかることがあり、その時には手遅れになっている場合が多いと、撤回プロセスを迅速化するための新たなガイドラインを最近発表した出版倫理委員会(COPE)のナンシー・チェシャイア委員長は述べている。
「編集者は、論文がシステマティック・リポートや臨床ケアに取り込まれる前に、より迅速に撤回する必要があります。そして、実際にそうした事態が起こっています」とチェシャイア委員長はRCIに語った。
しかし、科学文献の整理は、毎年爆発的に増加する論文数と矛盾している。
特に、論文作成業者の侵入を受けやすい、あまり権威のないジャーナルの編集者は多忙で、論文撤回の必要性を判断する複雑な作業に迅速に対応する時間とリソースがないと、2つの生物医学ジャーナルの編集長を務めたチェシャイア氏は語る。
チェシャイア氏は、出版社は特に資金不足に苦しむ発展途上国のジャーナルの公正性を守るために、より多くの資源を投入する必要があると述べている。例えば、ワイリーはヒンダウィの買収を通じて中国のジャーナルを所有している。
「研究のグローバル化は素晴らしいことだが、世界中の誠実性の問題に対処するのに十分なリソースを提供することに関しては、まだ遠い道のりだ」とチェシャイア氏は語った。
ビッグファイブからの脱却
少数のジャーナルは、その誠実さを守る最善の方法は商業出版から離脱することだと判断した。
1980年代以降、約38誌の編集委員会が、主にビッグファイブからの独立を宣言し、通常は新しい名称で運営されていると、オタワ大学でこの傾向を研究している博士課程の学生、サスキア・ヴァン・ヴァルサム氏は述べる。
スティルツ氏の哲学ジャーナルを含む最近の離脱の波において、出版社による論文掲載数の増加の圧力は大きな不満の種となっていた。
スティルツ氏の後継誌であるフリー・アンド・イコールは、「ダイヤモンド・オープンアクセス」と呼ばれる学術出版の代替アプローチを採用しており、これは何世紀も前に学者が主導権を握っていた時代を彷彿とさせます。
これは、学者が論文を出版するために費用を負担すべきではない、また一般の人々が論文を読むために費用を負担すべきではないという原則に基づき、数千もの小規模ジャーナルが展開する運動です。
『Free&Equal』を出版する非営利団体、オープン・ライブラリー・オブ・ヒューマニティーズ(OLH)は、ビッグ・ファイブの出版料金高騰に対処するため、2013年に設立されました。
アイビーリーグや米国・英国の主要公立大学を含む約350の図書館が、34タイトルの出版費用をOLHに支払う割合がビッグ・ファイブに比べて比較的低いことから、OLHを支援しています。
非営利出版の経済的側面は確かに健全ですが、2024年に創刊されたFree&Equalのような独立系ジャーナルは、評判を大きく損なうという課題に直面しています。
若手研究者はキャリアを築くために権威あるジャーナルに論文を発表する必要があり、Free&Equalのような新しいジャーナルが研究者への影響力を示すインパクトファクターを獲得するには数年かかることもあります。
スティルツ氏によると、彼女の新しい政治哲学ジャーナルは好調なスタートを切り、以前のWiley誌とほぼ同数の投稿を獲得しています。
「大量辞職をするときは、コミュニティが賛同してくれると信じなければなりません」と彼女は言った。
「あなたにはブランドがないのですから」 November 11, 2025
小平市の住宅地データセンター建設計画ですが、着工予定の2025年9月を過ぎても延期で全てが未定のままになってるんですね。
印西ファイブと同じ三井物産(担当者も同じ)だったので気になっていました。
事業主が合同会社かつ全ての予定が未定となっているので、ある程度地元と話がついたらフィデリティ/Coltに話を持っていって資金調達後、特定目的会社を立てるつもりだったところ、印西ファイブで大揉めとなり新規のDCプロジェクトを紹介どころかそんなのやってる場合じゃないとなった感じなんでしょうか。(合同会社は土地をとりあえず押さえるためのブリッジ?)
Colt DCSとESRとのJVが発表される直前に印西4をkeppel DC REITに売却してますがESRもKeppelもシンガポール資本かつ再編が進むシンガポールREIT市場で中心的なプレイヤー同士ですし、また、印西4には15年契約でマイクロソフトがシングルテナントとして入ってるので、適当に見つけたアセットマネージャーでは売却は躊躇われるというのを考えると資本関係はないにしろこの2社はかなり近しい間柄なんだろうなと想像に難くないです。(三井物産JV精算&箕面市のDC開発のための資金調達?)この状況で小平市のプロジェクト計画において三井物産がここから計画を前に進めるのはかなり厳しそうな気がします。
小平市の事例は、事業主が「資金」や「パートナー」の確保もままならない状態で見切り発車でプロジェクトを立ち上げ公表し、結果として地域をかき回したあげく塩漬けにして迷惑をかけている実態があります。 これは地域住民にとっても、土地の有効活用という観点からも、極めて「無責任」な行為だと私は思います。 November 11, 2025
ベルリンでは再び首脳会議の季節が到来した。自動車業界と鉄鋼業界との危機対応会議を経て、火曜日の注目は次の課題、デジタル経済へと移った。
これまでのところ、EU規制当局は文字通りデジタル経済を締め上げている。
ベルリンのEUREFキャンパスで盛大な歓迎会が行われました。ヨーロッパ各地の政財界、科学界から約900名の参加者が、デジタルサミットのためにベルリンに集まりました。
著名な講演者の中には、現在国内で厳しい政治的逆風に直面しているフリードリヒ・メルツ首相とフランスのエマニュエル・マクロン大統領もいました。
EUは今や政治レベルでも正式に危機モードに突入した。経済サミットの多さがこれを反映しており、今後数年間の暗い兆しを示唆している。
次なる大きな経済革命の火付け役となったデジタル経済を見れば、ブリュッセル、パリ、ベルリンのパニック状態は当然と言えるだろう。
ユーロ圏経済と米国および中国の競合国との間の技術格差は、現時点では埋められないように思われる。革命?その兆しは見えない。
活気のない資本市場
ベルリンでの演説から、欧州政策のジレンマが鮮明に浮かび上がった。
当初から規制枠組みは厳格すぎ、イノベーションを阻害し、デジタル経済は主にAmazon、Google、Microsoftといったアメリカの巨大企業に依存する形になってしまった。
SAPソフトウェアだって、アメリカから来ることが多いのだ!
したがって、サミットの中心的な要求は、強力な海外の競争相手への依存を減らすことであった。
欧州委員会は首脳会議当日、今後12ヶ月間にわたり、MicrosoftAzureやAmazonWebServicesといったクラウドプロバイダーによる反競争的行為とされる行為を、より厳格な規制によってどのように抑制できるかを検討すると発表した。
米国政府からの強力な反撃は確実であり、厳しい戦いが待ち受けている。
一方、メルツ首相は欧州のデジタル主権の確立を改めて訴え、米国製ソフトウェアへの依存に警鐘を鳴らした。
「デジタルの未来を積極的に形作ることが重要であり、競争相手との差を縮めるための追い上げプロセスを開始することが重要だ」と改めて強調した。
国家介入
欧州の政治家たちは、お決まりの結論、つまり公的資金投入という結論に至りました。
公的資金は既に欧州におけるAI全体の約40%を占めており、今後は欧州のIT人材の育成と維持にますます重点を置くことになるでしょう。
また、欧州経済のもう一つの弱点であるクラウドサービスやサイバーセキュリティを中心に、独立したデジタルインフラの構築にも役立つはずだ。
業界団体Bitkomは、EUのデジタル法の抜本的な簡素化と報告義務の大幅な削減を求めています。
GDPRは、ブリュッセルの過剰規制の他の要素と同様に、多大な費用をかけて無意味な失敗に終わりました。
AI法やデータ法など、あらゆる法律を見直し、合理化するか、廃止すべきです。
デジタル税は究極の政策か?
現状では、EUのデジタル経済は規模を拡大したり、国際的な競争相手に追いついたりすることが不可能です。
もう一つの論点は、グローバル企業、特に米国企業の広告収入に対するデジタル税です。
最近、ヴォルフラム・ヴァイマル文化大臣がこの構想を物議を醸す形で提案しました。
しかし、それで実際に何が変わるのでしょうか?ヨーロッパでは、国家がイノベーションを阻害しています。
公的機関を通じて流入する資本が多すぎるため、これらのイノベーションに資金を提供できる機能的なベンチャーキャピタル市場が生まれる余地がありません。
サミット参加者は、EUがトレードオフに直面していることを認識したと思われる。
最大限のデータ保護は産業の成長を阻害する。EUはデータの自由化を進め、ユーザー主導のデータ管理権を取り戻す必要がある。
水曜日には、この問題がブリュッセル議会の議論の中心となるだろう。
エネルギーとイノベーション文化
未来の経済はデータ主導型であり、安定したエネルギーインフラと、テクノロジーハブを取り囲む競争力の高いスタートアップ企業に依存します。
しかし、現在のドイツにはこれらが全く存在しません。
その結果、国際投資家はドイツという立地にほとんど関心を示していません。
欧州単一市場の規模、残存する資本力、そして強固な学術構造を考慮すると、デジタル経済をこれほどまでに完全に締め付けたのは政治的偉業と言えるでしょう。
ブリュッセルは、大規模なデジタル経済が存在するずっと前から規制の枠組みを構築していました。
自由市場の管理と操作に関しては、ブリュッセルは効率的かつ破壊的な行動をとっています。
委員会の撤退が必要
この規制の罠から抜け出し、デジタル起業家精神を刺激するには、悪しき慣行からの根本的な脱却が必要です。
つまり、AI法やGDPRのような規則を廃止し、欧州のデジタル市場を詳細に規制するデジタルサービス法(DSA)やデジタル市場法(DMA)による進行中の介入を停止する必要があります。
しかし、サミットでは、自ら作り出した問題への洞察はほとんど示されなかった。
ブリュッセルは、DSAとDMAへの批判の高まりを自らの権力への攻撃と捉えている。
デジタル規制は、気候変動政策と同様に、ユーロ経済のイデオロギー的再構築という文脈で捉えなければならない。
ブリュッセルはこの致命的なプロセスの司令塔であり、景気後退の深刻化に伴い、規制当局への圧力は高まっている。
市場の障壁は撤廃され、起業家精神はより自由になり、財政負担は軽減され、国家は資本市場の支配から撤退しなければならない。
ベルリン・サミットでは、デジタル規制のゴルディアスの結び目を抜本的な自由化によって解き放ち、自律的な欧州のエコシステムの成長を可能にするという話は、まるで寓話のように聞こえた。
哲学の衝突
デジタル経済ほど、米国と欧州の政治哲学と経済パラダイムが激しく衝突した例は稀である。
ブリュッセルの検閲、DSA(欧州安全保障協力機構)、そして計画されているチャット監視をめぐる論争は、現実の緊張を引き起こし、2月のミュンヘン安全保障会議でJ・D・ヴァンス米副大統領が欧州の検閲を批判して以来、エスカレートしている。
デジタル空間では、公民権、言論の自由、そして財産権をめぐる争いが明らかに繰り広げられている。
自由対監視、自己責任対ナニー国家――米国対EU?大まかに言えば、そう解釈することもできる。
しかし、米国は自国のデジタル寡占の市場支配力、そして新規参入者が自由に市場にアクセスできるかどうか、あるいはブリュッセルのようにロビー活動によってAmazonなどが競争から守られているかどうかについても、対処しなければならない。
デジタルリスク空間
欧州の規制当局にとって、デジタル空間は何よりも物語上のリスクであり、反対意見を抑制するのではなくむしろ煽る、制限のない、規律が難しい公共空間である。
XやMetaなどの米国のプラットフォームに対するドイツの政治家による最近の攻撃は、EUの政治とイデオロギーにとって極めて重要な紛争分野、すなわち気候政策、ウクライナ紛争、深刻化する経済危機における意識の高まりと制御の喪失を反映しており、これらは国営メディアではほとんど報道されていない。
不透明で、分散的で、論争的で、非常に目立つ形で批判的な反対勢力が形成されるリスクは常に存在し続けています。
エラーと制御
ユーロ圏経済のデジタル未来に関する議論では、デジタルユーロの亡霊、そしてデジタル空間における個人の主権の問題が浮上している。
この技術を金融・資本市場における中央集権的な国家支配の一形態として統合しようとする試み自体が、ブリュッセルがデジタル技術を、最小限の国家規制のもとで発展する分散型競争の問題として理解していないことを示している。
ワシントンは、天才法と、準代替金融市場である銀行への米国ステーブルコインの統合により、信用創造を民間部門の責任にさらに深く押し進めている。
ヨーロッパの時代錯誤
すべてが、分散型通貨の創造と技術的なAIアプリケーションの同時融合を示しており、だからこそ、これらの要素を中央集権化し、厳しく規制しようとするEUの試みは失敗する運命にある。
デジタルサミットは、懸念を裏付けた。欧州の政策は、公的資金、詳細な規制、労働基準、厳しく検閲された公の言説がイデオロギーの青写真を形成するモデルに、知的かつ官僚的に閉じ込められているのだ。
技術の進歩が自由へと向かうならば、これは良い結末にはならないし、良い結末にはならないだろう。 November 11, 2025
【真相判明】AIバブル、「ババを引く」のはコイツだ(NVIDIA/オラクル/循環取引/Google/メタ/ネオクラウド/マイクロソフト/Open... https://t.co/sAoTN9nGO2 @YouTubeより 面白い笑 November 11, 2025
【医療データ研究者、関心のある自治体の皆さま】
お待たせしました🙂AJAPAを公開しました
当センターの村松圭司特任教授が前職からの異動にともない世の中に公開が止まっていた
『AJAPA』を千葉大当センターのサイトで再公開しました^_^
無料です、どんどん使ってください
※注意は必ずお読みくださいね※
https://t.co/wYdo1BLaLP
村松先生からコメントと注意の概要
↓↓
地域別人口変化分析ツール All Japan Areal Population-change Analyses(AJAPA)は「医療計画を踏まえた医療の連携体制構築に関する評価に関する研究(H24-医療-指定-037)」において、
研究代表者である松田晋哉(当時:産業医科大学 医学部 教授)と、
研究分担者である伏見清秀(東京医科歯科大学大学院・医療政策情報学分野 教授)によって提唱された推計方法によって将来患者を推計した結果を簡便に表示するために、
研究協力者の村松圭司(当時:産業医科大学 医学部 助教)がMicrosoft® excel®を用いて作成したものです。 November 11, 2025
11/21(金)☀️
おはようございます♪
毎日にわくわくと感動を✨
繋がりを大切に増やしたい🥇
### 🔥今日の投資トピックス!2025/11/21 – AIブームが加速中?エヌビディア決算で市場が揺れる!💰📈
本日も市場のホットニュースをサクッとまとめました。米株がAI熱で沸騰中ですが、調整リスクもチラホラ…。あなたの本命株は?コメントで教えて! #投資 #株 #AI投資
1. MS&エヌビディア、AI企業に巨額投資!
マイクロソフトとエヌビディアがAnthropicに最大150億ドル(約2.3兆円)投資へ!AI分野の競争がさらにヒートアップ。テック株ホルダー歓喜?でも過熱警戒⚠️
2. エヌビディア決算発表で市場注目!
20日の決算で株価変動予想大。マグニフィセント7の期待値高すぎて、失望売りのリスクも。S&P500の上昇はこれら7社頼み…倭国株への波及に要警戒!📉
3. 2025年投資信託おすすめ5選公開!
みんかぶが厳選。デジタル産業やグローバル株中心に、初心者も狙える銘柄満載。円安基調で海外分散のチャンス?今すぐチェック!🔥
来週の米経済指標も要チェック。トランプ政策の影も…。フォロー&RTで最新情報ゲット!あなたの投資戦略は? #日経平均 #投資初心者
---
### 🚀本日の中小企業トピックス!2025/11/21 – 2025年問題がヤバい?補助金で逆転のチャンス!🏭💪
中小企業戦士の皆さん、闘う1日お疲れ![あなたの名前]が今日のニュースをピックアップ。廃業ラッシュの危機だけど、政府支援が熱い!あなたの会社、どう乗り切る?シェアしようぜ! #中小企業 #事業承継 #DX
1. 事業承継・M&A補助金第13次公募スタート!
中小企業庁が革新支援の補助金募集。M&Aで資源引き継ぎや廃業再チャレンジをバックアップ!後継者不在の245万社が狙い目。早速申請を!📝
2. 2025年問題で廃業急増…対策はM&A?
団塊世代引退で高齢経営者急増。人手不足&後継者不足が深刻。親族承継減少中だけど、M&A件数は4.4倍に!売上100億宣言で補助金最大5億円も夢じゃないよ🔥
3. 中小企業白書2025:経営力UPでスケールアップ!
円安・物価高・人手不足の厳しい環境下、経営者の「経営力」強化が鍵。DXツール導入で生産性爆上げ!優秀新技術賞も募集中。挑戦の年だ!🚀
廃業じゃなく成長を選ぼう!セミナーやツール活用で一歩前進。いいね&フォローで仲間増やそう! #2025年問題 #中小企業支援
---
### 🏠本日の不動産トピックス!2025/11/21 – 投資額6兆円超え!? 気候リスクが新たな脅威…🏘️🌪️
不動産好きの[あなたの名前]です!今日の市場は投資ブーム継続中だけど、気候変動の影が…。あなたは買う?売る?ディスカッション待ってます! #不動産 #投資 #リノベ
1. 2025年不動産投資市場:6兆円突破の兆し!
JLL予測で過去最高額へ。需要・供給バランスが投資家有利。オフィス回帰&データセンター需要が後押し!下半期チャンス到来?💹
2. 気候変動で不動産業界大転換!
JLLレポート:BCP強化&レジリエンスUPが急務。AIブームでデータセンター爆増だけど、洪水・地震リスク高まる。地方空き家問題も深刻化…対策必須⚠️
3. 新ブランド「HAMMONS」デビュー!調布に264戸
京王電鉄&リビタの分譲マンション。リノベ会社「リテラム」も始動で、古民家再生ブーム?高齢者向け住宅需要も熱い!🏡
暴落懸念あるけど、トレンド掴めば勝ち組。RTで情報拡散!あなたの不動産投資話、聞かせて! #不動産投資 #空き家 #サステナブル
中小企業やスタートアップ、そして会社員にとって、時間は最も有限で貴重な資源であり、自ら環境を変える挑戦こそが、その使い方と成長の度合いを自分次第で決定する唯一の方法てす!
#会社員投資家 #アドバイザー
#コンサルタント #会社員不動産投資家
#JUNENAGROUP #トピックス #中小企業支援 #スタートアップ支援 #販売戦略 #顧問 #サービス November 11, 2025
surface pro12のキーボード+ペン+ケースのセットが美品で出てるよ~!誰か買って一緒にカフェで推し活しない??笑
Microsoft surface pro12 2025用社外オプションセット
https://t.co/jkKPYmSR83 November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。