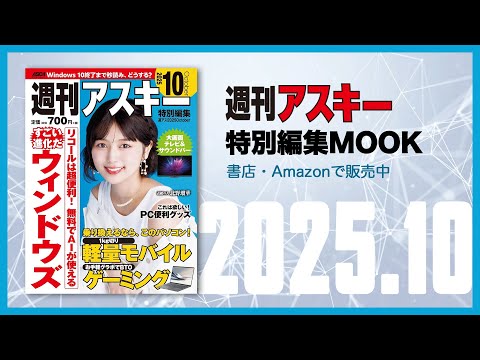クラウド
0post
2025.11.26 00:00
:0% :0% (40代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
衝撃⚡️まじでヤバい💔
【渋谷発 次世代テック/エコシステム構築】
効率化の鬼&AI芸人で有名な大人気講師
モーリー氏@skillfreakdx
カスタマークラウドに特別枠で正式参画🚀
第2のビットバレー構想、いよいよ“人材集積フェーズ”へ ―
この最後の波に気付き乗れるか否か。
まもなく、倭国が返り咲く🇯🇵🌸‼️
https://t.co/zILvEtIfEm @PRTIMES_JP November 11, 2025
28RP
Windows10から11へのアップデートで、リリース当初より愛用していたGoogle倭国語入力が絶望的なまでに変換能力を低下させ、あまりにも使い物にならなかったので、この一カ月でATOKとMS倭国語入力を使い比べてみた結果の寸評。
ATOK:現時点での変換能力は一番高いように感じるのだが、年間7200円支払うほどの性能差は感じられない。アホな変換は普通にしまくるので、値段相応に素晴らしく快適とは思わなかった。あとブラウザを強制終了が頻発するのは俺の個人環境だけかな?
MS倭国語入力:特別優秀だと思うことは無いのだが、無料と思えば十分な気もする。動作の重さを感じる瞬間が稀にあるが、気にならないレベル。ショートカット登録などインターフェイスのカスタマイズ余地がほぼ無いのが凄く困る。
Google倭国語:この前まではなんの不満もなかったのが、Windows11にした途端唐突に絶望的な変換をお出ししてくるようになり、最初は自分が脳の病気にでもなったのかとマジで心配になった。クリーンな再インストールしても無駄。キャラや作品名など様々な固有名詞が自動的にクラウド辞書として登録される機能はどの倭国語入力も備えているようだが、それに関してはGoogle倭国語入力がずば抜けて高い。それは今もそう。だが本当に変換能力が終わってる。そしてGoogle側にアップデートする気がほぼ無いのが絶望を加速させる。 November 11, 2025
6RP
【DLsite】購入済みPCゲーム2万作品がスマホでプレイ可能に
https://t.co/np3xK14FFy
追加費用なし・インストール不要のクラウド方式で場所を選ばず楽しめる。期間限定キャンペーンは11月30日まで開催中。 https://t.co/ECQBlYTSvl November 11, 2025
5RP
Gemini3, Nano Banana Pro登場で, 先月時点で私がTBSの以下番組で「OpenAIは危うい.Googleが勝つ」としてたのが注目(特に投資家層?)されてるようです
実際は公には以下記事で2024年OpenAI絶頂期からずっとGoogle有利とみてます
長い(私のX史上最長)ですが根拠, OpenAI vs Googleの展望を書いてみます
先月のTBS動画:https://t.co/kgWcyTOTWK
2024年6月の記事:https://t.co/4HEhA4IJQa
参考のため、私がクローズドな投資家レクなどで使う資料で理解の助けになりそうなものも貼っておきます。
※以下はどちらかというと非研究者向けなので、研究的には「当たり前では」と思われることや、ちょっと省略しすぎな点もあります。
まず、現在の生成AI開発に関して、性能向上の根本原理、研究者のドグマ的なものは以下の二つです。基本的には現在のAI開発はこの二つを押さえれば大体の理解ができると思います。両者とも出てきたのは約5年前ですが、細かい技術の発展はあれど、大部分はこの説に則って発展しています。
①スケーリング則
https://t.co/WKl3kTzcX5
②SuttonのThe Bitter Lesson
https://t.co/esHtiJAcH9
①のスケーリング則は2020年に出てきた説で、AIの性能は1)学習データの量、2)学習の計算量(=GPUの投入量)、3)AIのモデルサイズ(ニューラルネットワークのパラメータ数)でほぼ決まってしまうという説です。この3つを「同時に」上げ続けることが重要なのですが、1と3はある程度研究者の方で任意に決められる一方、2のGPUはほぼお金の問題になります。よって、スケーリング則以降のAI開発は基本的にお金を持っている機関が有利という考えが固まりました。現在のChatGPTなどを含む主要な生成AIは一つ作るのに、少なく見積もってもスカイツリーを一本立てるくらい(数百億)、実際には研究の試行錯誤も含めると普通に数千億から数兆かかるくらいのコストがかかりますが、これの大部分はGPUなどの計算リソース調達になります。
②のThe Bitter Lessonは、研究というよりはRichard Suttonという研究者個人の考えなのですが、Suttonは現在のAI界の長老的な人物で、生成AI開発の主要技術(そして私の専門)でもある強化学習の事実上の祖かつ世界的な教科書(これは私達の翻訳書があるのでぜひ!)の執筆者、さらにわれわれの分野のノーベル賞に相当するチューリング賞の受賞者でもあるので、重みが違います。
これは端的にいうと、「歴史的に、AIの発展は、人間の細かい工夫よりも、ムーアの法則によって加速的に発展する計算機のハードの恩恵をフルに受けられるものの方がよい。つまりシンプルで汎用的なアルゴリズムを用い、計算機パワーに任せてAIを学習させた方が成功する。」ということを言っています。
①と②をまとめると、とにかく現状のAIの性能改善には、GPUのような計算リソースを膨大に動員しなければならない。逆に言えばそれだけの割と単純なことで性能上昇はある程度約束されるフェーズでもある、ということになります。
これはやや議論を単純化しすぎている部分があり、実際には各研究機関とも細かいノウハウなどを積み重ねていたり、後述のようにスケーリングが行き詰まることもあるのですが、それでも昨今のAI発展の大半はこれで説明できます。最近一般のニュースでもよく耳にするようになった異常とも言えるインフラ投資とAIバブル、NVIDIAの天下、半導体関連の輸出制限などの政治的事象も、大元を辿ればこれらの説に辿り着くと思います。
以下、この二つの説を前提に話を進めます。
公にはともかく私が個人的に「OpenAIではなくGoogleが最終的には有利」と判断したのはかなり昔で、2023年の夏時点です。2023年6月に、研究者界隈ではかなり話題になった、OpenAIのGPT-4に関するリーク怪文書騒動がありました。まだGoogleが初代Geminiすら出してなかった時期です。(この時期から生成AIを追っている人であれば、GPT-4のアーキテクチャがMoEであることが初めて明らかになったアレ、と言えば伝わるかと思います)
ChatGPTの登場からGPT-4と来てあれほどの性能(当時の感覚で言うと、ほぼ錬金術かオーパーツの類)を見せられた直後の数ヶ月は、さすがに生成AI開発に関する「OpenAIの秘伝のタレ説」を考えており、OpenAIの優位は揺らがないと考えていました。論文では公開されていない、既存研究から相当逸脱した特殊技術(=秘伝のタレ)がOpenAIにはあって、それが漏れない限りは他の機関がどれだけお金をかけようが、まず追いつくのは不可能だと思っていたのです。しかし、あのリーク文書の結論は、OpenAIに特別の技術があったわけではなく、あくまで既存技術の組み合わせとスケーリングでGPT-4は実現されており、特に秘伝のタレ的なものは存在しないというものでした。その後、2023年12月のGemini初代が微妙だったので、ちょっと揺らぐこともあったのですが、基本的には2023年から私の考えは「最終的にGoogleが勝つだろう」です。
つまり、「スケーリングに必要なお金を持っており、実際にそのAIスケーリングレースに参加する経営上の意思決定と、それを実行する研究者が存在する」という最重要の前提について、OpenAIとGoogleが両方とも同じであれば、勝負が着くのはそれ以外の要素が原因であり、Googleの方が多くの勝ちにつながる強みを持っているだろう、というのが私の見立てです。
次に、AI開発競争の性質についてです。
普通のITサービスは先行者有利なのですが、どうもAI開発競争については「先行者不利」となっている部分があります。先行者が頑張ってAIを開発しても、その優位性を保っている部分でAIから利益を得ることはほとんどの場合はできず、むしろ自分たちが発展させたAI技術により、後発事業者が追いついてきてユーザーが流出してしまうということがずっと起きているように思われます。
先ほどのスケーリング則により、最先端のAIというのはとても大きなニューラルネットワークの塊で、学習時のみならず、運用コストも膨大です。普通のITサービスは、一旦サービスが完成してしまえば、ユーザーが増えることによるコスト増加は大したことがないのですが、最先端の生成AIは単なる個別ユーザーの「ありがとうございます」「どういたしまして」というチャットですら、膨大な電力コストがかかる金食い虫です。3ドル払って1ドル稼ぐと揶揄されているように、基本的にはユーザーが増えれば増えるほど赤字です。「先端生成AIを開発し、純粋に生成AIを使ったプロダクトから利益を挙げ続ける」というのは、現状まず不可能です。仮に最先端のAIを提供している間に獲得したユーザーが固定ユーザーになってくれれば先行者有利の構図となり、その開発・運営コストも報われるのですが、現状の生成AIサービスを選ぶ基準は純粋に性能であるため、他の機関が性能で上回った瞬間に大きなユーザー流出が起きます。現状の生成AIサービスはSNSのように先行者のネットワーク効果が働かないため、常に膨大なコストをかけて性能向上レースをしなければユーザー維持ができません。しかも後発勢は、先行者が敷いた研究のレールに乗っかって低コストで追いつくことができます。
生成AI開発競争では以上の、
・スケーリング則などの存在により、基本的には札束戦争
・生成AIサービスは現状お金にならない
・生成AI開発の先行者有利は原則存在しない
と言う大前提を理解しておくと、読み解きやすいかと思います。
(繰り返しですがこれは一般向けの説明で、実際に現場で開発している開発者は、このような文章では表現できないほどの努力をしています。)
OpenAIが生成AI開発において(先週まで)リードを保っていた源泉となる強みは、とにかく以下に集約されると思います。
・スケーリングの重要性に最初に気付き、自己回帰型LLMという単なる「言語の穴埋め問題がとても上手なニューラルネットワーク」(GPTのこと)に兆レベルの予算と、数年という(AI界隈の基準では)気が遠くなるような時間を全ベットするという狂気を先行してやり、ノウハウ、人材の貯金があった
・極めてストーリー作りや世論形成がうまく、「もうすぐ人のすべての知的活動ができるAGIが実現する。それを実現する技術を持っているのはOpenAIのみである」という雰囲気作りをして投資を呼び込んだ
前者については、スケーリングと生成AIという、リソース投下が正義であるという同じ技術土俵で戦うことになる以上、後発でも同レベルかそれ以上の予算をかけられる機関が他にいれば、基本的には時間経過とともにOpenAIと他の機関の差は縮みます。後者については、OpenAIがリードしている分には正当化されますが、一度別の組織に捲られると、特に投資家層に対するストーリーの維持が難しくなります。
一方のGoogleの強みは以下だと思います。
・投資マネーに頼る必要なく、生成AI開発と応用アプリケーションの赤字があったとしても、別事業のキャッシュで相殺して半永久的に自走できる
・生成AIのインフラ(TPU、クラウド事業)からAI開発、AIを応用するアプリケーション、大量のユーザーまですべてのアセットがすでに揃っており、各段階から取れるデータを生かして生成AIの性能向上ができる他、生成AIという成果物から搾り取れる利益を最大化できる
これらの強みは、生成AIのブーム以前から、AIとは関係なく存在する構造的なものであり、単に時間経過だけでは縮まらないものです。序盤はノウハウ不足でOpenAIに遅れをとることはあっても、これは単に経験の蓄積の大小なので、Googleの一流開発者であれば、あとは時間の問題かと思います。
(Googleの強みは他にももっとあるのですが、流石に長くなりすぎるので省略)
まとめると、
生成AIの性能は、基本的にスケーリング則を背景にAI学習のリソース投下の量に依存するが、これは両者であまり差がつかない。OpenAIは先行者ではあったが、AI開発競争の性質上、先行者利益はほとんどない。OpenAIの強みは時間経過とともに薄れるものである一方、Googleの強みは時間経過で解消されないものである。OpenAIは自走できず、かつストーリーを維持しない限り、投資マネーを呼び込めないが、一度捲られるとそれは難しい。一方、GoogleはAIとは別事業のキャッシュで自走でき、OpenAIに一時的に負けても、長期戦でも問題がない。ということになります。
では、OpenAIの勝利条件があるとすれば、それは以下のようなものになると思います。
・OpenAIが本当に先行してAGI開発に成功してしまう。このAGIにより、研究開発や肉体労働も含むすべての人間の活動を、人間を上回る生産性で代替できるようになる。このAGIであらゆる労働を行なって収益をあげ、かつそれ以降のAIの開発もAGIが担うことにより、AIがAIを開発するループに入り、他の研究機関が原理的に追いつけなくなる(OpenAIに関する基本的なストーリーはこれ)
・AGIとまではいかなくとも人間の研究力を上回るAIを開発して、研究開発の進捗が著しく他の機関を上回るようになる
・ネットワーク効果があり先行者有利の生成AIサービスを作り、そこから得られる収益から自走してAGI開発まで持っていく
・奇跡的な生成AIの省リソース化に成功し、現在の生成AIサービスからも収益が得られるようになる
・生成AI・スケーリング則、あるいは深層学習とは別パラダイムのAI技術レースに持ち込み技術を独占する(これは現在のAI研究の前提が崩れ去るので、OpenAI vs Googleどころの話ではない)
・Anthropicのように特定領域特化AIを作り、利用料金の高さを正当化できる価値を提供する
最近のOpenAIのSora SNSや、検索AI、ブラウザ開発などに、この辺の勝利条件を意識したものは表れているのですが、今のところ成功はしていないのではないかと思います。省リソース化に関しては、多分頑張ってはいてたまに性能ナーフがあるのはこれの一環かもしれないです。とはいえ、原則性能の高さレースをやっている時にこれをやるのはちょっと無理。最後のやつは、これをやった瞬間にAGIを作れる唯一のヒーローOpenAIの物語が崩れるのでできないと思います。
最後に今回のGemini3.0やNano Banana Pro(実際には二つは独立のモデルではなく、Nano Bananaの方はGemini3.0の画像出力機能のようですが)に関して研究上重要だったことは、事前学習のスケーリングがまだ有効であることが明らかになったことだと思います。
ここまでひたすらスケーリングを強調してきてアレですが、実際には2024年後半ごろから、データの枯渇によるスケーリングの停滞が指摘されていること、また今年前半に出たスケーリングの集大成で最大規模のモデルと思われるGPT-4.5が失敗したことで、単純なスケーリングは成り立たなくなったとされていました。その一方で、
去年9月に登場したOpenAIのo1やDeepSeekによって、学習が終わった後の推論時スケーリング(生成AIが考える時間を長くする、AIの思考過程を長く出力する)が主流となっていたのが最近です。
OpenAIはそれでもGPT-5開発中に事前学習スケーリングを頑張ろうとしたらしいのですが、結局どれだけリソースを投下しても性能が伸びないラインがあり、諦めたという報告があります。今回のGemini3.0に関しては、関係者の発言を見る限り、この事前学習のスケーリングがまだ有効であり、OpenAIが直面したスケーリングの限界を突破する方法を発見していることを示唆しています。
これはもしかしたら、単なるお金をかけたスケーリングを超えて、Googleの技術上の「秘伝のタレ」になる可能性もあり、上記で書いた以上の強みを今回Googleが手にした可能性もあると考えています。
本当はもっと技術的に細かいことも書きたいのですが、基本的な考えは以上となります。色々と書いたものの、基本的には両者が競争してもらうことが一番技術発展につながるとは思います! November 11, 2025
4RP
クラウドナイン
千木良社長さんポストの
四枚目、『Ado保護者会』の
『君にドレスの花束を』をテーマに
凱旋帰国お帰り!のシーンで
イラストを描かせて頂きました🥹💙🙇♀️
スポンサーボードも🥰
Adoちゃん✨本当におかえり…!
保護者会の皆さま、
ありがとうございました🙇♀️✨
#フラワースタンド https://t.co/7pRjZAWrbI https://t.co/Sty4v3sMPm November 11, 2025
2RP
大筋では結局この通りで、GeminiとGPTが汎用とコーディングの両方でぶち抜き始めたことで、いよいよClaudeとしてはコーディングだけは負けるわけにはいかん(今となってはほぼ唯一の強み)ということで押し込まれて、Opus 4.5がその答えなんだろうな。
もう確定的にエンジニア向けに特化せざるを得ない感じ。
逆を言えば今となってはGPTとClaudeを両方持ってる唯一のクラウドであるAzureのカバレッジがこれまでになく良い感じになってる。 November 11, 2025
1RP
#思写EXPO #オモ写EXPO後夜祭
中学の時の同級生たちと一緒に作ったカードゲーム『クラウドロウ』です。
まさに思い出のオモチャです。 https://t.co/5BNTiwgh9D November 11, 2025
1RP
本日11/25の参議院総務委員会より、ガバメントクラウド・自治体システム標準化に関する質疑を以下に抽出。(YouTube文字起こしをGeminiで清書したもの)
==
高木佳保里 委員
自治体システム標準化とガバメントクラウドについて伺います。
約2年前となる令和5年、私はこの総務委員会で「政府として国産クラウドを本気で押し進めていくことが必要である」という観点から、政府と地方自治体システムの共通基盤となるガバメントクラウドについて取り上げさせていただきました。複雑化する国際情勢を背景に、経済安全保障の観点から、国としても国産クラウドを育成する重要性はこれまで以上に増大していると考えております。
令和4年から5年にかけて、ガバメントクラウドの対象として5件のクラウドサービスが採用されましたが、そのうち国産クラウドは「さくらインターネット株式会社」の1件のみであり、その他は全てAmazon、Google、Microsoft、Oracleといった外資系企業が提供するサービスです。
このさくらインターネットについては、2025年度末までに全ての要件を満たす条件付きの採用であり、今年度内の要件達成が求められているのが現状かと存じます。そこで、さくらインターネットに対する政府支援や、技術要件などを含めた進捗状況はどうなっているのか確認させてください。
奥田 審議官(デジタル庁)
さくらインターネット株式会社の「さくらのクラウド」につきましては、令和5年度のガバメントクラウドの調達において、2025年度末(今年度末)までに全ての技術要件を満たすことを条件として、国内事業者として初めて採用したところでございます。
さくらのクラウドにつきましては、四半期ごとに開発計画の進捗状況について審査することとしており、2025年9月末時点の進捗状況を確認したところ、開発計画全体に影響のある遅れはなく、順調な開発進捗となっていることを確認し、11月7日にデジタル庁ホームページでも公表させていただいたところです。
さくらのクラウドがガバメントクラウドとして求められる技術要件をクリアして本番稼働が可能となることをデジタル庁としても期待しておりますし、今後も2025年度末に向けてしっかりと進捗を把握してまいります。
高木佳保里 委員
政府として、競争性の確保と国産クラウドの育成の重要性の両方を認識されているとは思いますが、経済安全保障の観点からも情報通信に関する国産クラウドを育成していくことは、国がしっかりと後押しをしていくべきですので、是非この点も留意していただきたいと思います。
次に、ガバメントクラウドに関連して、コスト面について伺います。
今月11日、私の地元である大阪の知事、市長会長、町村会会長より連名で、総務大臣及びデジタル大臣宛てに「地方公共団体情報システム標準化の推進に向けた支援」についての要望書が提出されたと承知しております。
本年6月13日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、地元現場からは、標準化によってかえってランニングコスト(運営経費)が増大するという懸念が強く示されているわけです。要望書においても「移行経費」及び「移行後の運用経費」の増嵩(ぞうすう)が大きな負担となる旨が明確に示されています。
従来のオンプレミスからガバメントクラウドへ移行することで、回線使用料やクラウド利用料が恒久的に発生します。昨今の円安やベンダー側の価格改定等によって、コスト上昇リスクが顕在化しているのが現状です。
こうした運用経費の増嵩という現実を総務大臣はどのように受け止めているか伺いたい。合わせて、システム移行にかかる初期経費及びこのランニングコストの増大部分については、国がしっかりと支援すべきと考えますが、いかがでしょうか。
林 総務大臣
自治体情報システムの標準化に関しましては、基金を設置した上で、国費10/10の補助金により、標準準拠システムへの移行に要する経費を支援しております。令和6年度補正予算後で、総額7,182億円を確保しているところです。事業者の人的資源の逼迫などにより、令和8年度以降の移行とならざるを得ないシステムにつきましても、引き続き支援を行うべく、先の通常国会において法改正を行い、基金の設置期限を令和12年度末までに延長したところです。
ご指摘のありましたランニングコストにつきましては、今後必要となる一般財源総額をしっかり確保できるように対応してまいりたいと考えております。具体的な詳細はデジタル庁から答弁させます。
三橋 審議官(デジタル庁)
自治体システムの標準化・ガバメントクラウドへの移行に関しますランニングコストにつきましては、デジタル庁からお答えさせていただきます。
多くの自治体から、移行後の運用経費の増加に対するご懸念や財政支援を求める声があることは承知しております。移行後の運用経費は、本来自治体が現行システムで負担する運用経費に相当するものであることなどを踏まえまして、各自治体が負担することが基本ではございます。
その上で、デジタル庁としても本年6月に決定した「自治体システムの標準化・ガバメントクラウド移行後の運用経費にかかる総合的な対策」に基づきまして対応を進めております。具体的には、当面の対策として各自治体が行う見積もり支援の強化や、クラウド利用料の更なる割引交渉などを行っております。特に見積もり精査支援の強化につきましては、都道府県とデジタル庁で連携をして、より手厚い市区町村への支援を推進しております。
また、システム運用管理の自動化や競争環境の改善に向けたシステム運用経費の見える化・分析など、構造的な要因に対する対策で経費の抑制を図ってまいります。
さらに、こうした対策を講じてもなお増加する運用経費に対する財政措置につきましては、様々な制約がある中で、デジタル庁としても知恵を絞り、関係省庁と連携して検討を進めているところです。今回の経済対策におきまして「移行後の運用経費の増加への対応を含めて、安定的な運用のために必要な措置を講じる」と決定したことも踏まえまして、予算編成において具体的な措置についての検討を加速してまいります。
高木佳保里 委員
よろしくお願いしたいと思います。標準化対応によって多大な財政的負担が生じる中で、このままでは自治体のDX予算が標準化システムの維持費だけに食いつぶされてしまう恐れがあります。本来目指すべき住民サービスやスマートシティの実現に予算が回らないということになりかねません。「システムを標準化した結果、自治体が貧乏になってしまった」「独自の住民サービスが低下した」と言われることがないようにお願いしたいと思います。
毎年の交付税措置だけではなく、実費に見合った補助金と直接的な財政支援の枠組みもしっかりとお考えいただきたいと思います。
もう少しこの点について伺います。現在、クラウド基盤や仮想化ソフトの市場では、外資系ベンダーによるライセンス体系の変更や大幅な値上げが相次いでいると聞いています。いわゆる「クラウドフレーション」ということで、自治体財政を圧迫する要因となっているとお聞きしていますが、国が主導するガバメントクラウドを利用する以上、一自治体の交渉力ではどうにもなりません。
政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)の基準を満たす事業者が限られている中で、特定ベンダーによる事実上のロックインや一方的な値上げに対して、国としてどう自治体をサポートしていくのか伺います。
奥田 審議官(デジタル庁)
ガバメントクラウドの調達にあたりましては、一度採用したクラウドサービスにロックインされることのないように、データが容易に移行できるツールや仕組みがあること、技術情報が公開されることを調達仕様書で求めるなど、特定クラウドから他のクラウドへの移行が困難とならないよう、いわゆるロックイン防止の対応を行っているところです。
また、ガバメントクラウドの利用料にかかる契約等につきましてはデジタル庁が一括して行っており、クラウドサービス事業者との交渉等は全てデジタル庁が行っております。
ご質問の一方的な値上げ対策としましては、クラウドを構成する各事業者とデジタル庁とのクラウドサービス基本契約におきまして、契約の変更等を行う場合には事前に協議を行うこととしており、クラウドサービス提供事業者が一方的に利用料を設定することはできないようにしているところです。 November 11, 2025
1RP
/
Wフォロー&リポスト🔁で
A5ランク【黒】毛和牛🐃
#プレゼントキャンペーン 🎁⚡️
\
📢 応募方法
①クラウドキャッチャー & モコネオ をWフォロー!
@CCatcherApp & @CC_moconeo
② キャンペーン投稿をリポスト🔁
🗓️ 期間:〜11月28日(金)23:59〆
🏆 賞品:A5 黒毛和牛 選べるカタログギフト…抽選1名様
🔽詳細はこちら🌩️
https://t.co/wXPx2dqdwB
#クラウドキャッチャー
#オンラインクレーンゲーム #オンクレ
#ブラックフライデー
#リポストキャンペーン November 11, 2025
1RP
よみうりランドに行ってきた
スピンランウェイのスピンが凄いと聞いたのでドキドキで乗ったけど叫んだり笑ったりで楽しかった~🤭カワウソ🦦にも会えて…でもあんなに動き回るなんてビックリ🤣友梨奈ちゃんの自引きはできなかったけど楽しい1日でした💕
> #クラウドナインパーク
#平手友梨奈 https://t.co/3qx4J7ke4V November 11, 2025
1RP
定期的に言ってるけどサイボウズはホントすごい会社だと思うな。
・オンプレ→クラウドのイノベーションのジレンマを完全に克服
・AWSとかじゃなくてデータセンター自前運用
・MS、Google、Salesforceとガチ競合する領域
・そんなハード過ぎる状況で↓の成長を継続
僕は2011年〜2016年までGoogleのクラウド部門にいて、中小企業向けの営業担当だったので、まさに彼らがオンプレからクラウドにチャレンジをする、というニュースを競合として見ていたんだけど、ぶっちゃけ当時は「サイボウズですか?GoogleとかSalesforceとの競合はさすがにキツイんじゃないですかね?」とかなり確信度高く思っていたし、お客さんとも喋っていたんだけど、まさかこんなに成長するなんて思っていなかった November 11, 2025
1RP
えー!あのオンのクラウドモンスターハイパー、パリ五輪限定モデルが売られてる!ほしいけど、26.0かあ…誰か買っちゃってー!
【26.0】 ON Cloudmonster クラウドモンスター ハイパー
https://t.co/0LM0PfwpZB November 11, 2025
クラウドだけリミットが溜まっていなかった理由、他の仲間はエアリスをころされたと思っているから怒っているけど、クラウドはエアリスは生きていると思っているし、「クラウドはだいじょうぶ(怒りや悲しみに飲まれないって信じている)」と言われ癒されたから、とかだったらいいなあ。 November 11, 2025
やっぱり映画やってくれ未成年。
クラウドなんちゃら必要なら金出すから。
それか、朝待ちの歌を2人でやるとか。俺達に似てる気がした言うくらいだから、ストーリーきになる。 November 11, 2025
ゼンゼロのクラウド版の体験案内がきてたから入れてみたけど解像度良すぎてやばいなw
くっきりハッキリつやてかでぬるぬる動く!
スマホでPC版の画質が楽しめる感じだこれ
←いつもの クラウド版→ https://t.co/IIJAqYqGXw November 11, 2025
【3/3】
要するに「完璧を求めない」「AIに教えてもらう」「会話する」だけ。
+αで「何度も聞き直す」が最強なんだけど、それは需要があれば今度書きます。
とにかく生成AIよく分からないって人はチャッピーが今年の流行語対象になってるくらいだから今すぐ触って体験してみた方がいい。
勉強してから…って言ってる人は来年確実に置いてかれるよ。本も大事だけど使うだけならすぐ使える。AtlasのWindows版も来るかもだし、とにかく触ってみよう。
個人的に最近はチャッピーことChatGPTでざっくり作って、Claudeクラウドで表現直して、Geminiで深く聞く。それをチャッピーに戻して評価してって感じで使うことが多いですw
使う手間はありますが、やはり利用者が多いChatGPTが、最強だと思います。
#生成AI #ビジネス活用 #ChatGPT November 11, 2025
@kaze_no_ne_kazu 「クラウドの腕をとって凄いわ、クラウド!みたいな発言をしたエアリスとクラウドの後ろで寂しそうにうつむいていたティファ」
これに合致するシーンはFF7にはありませんので、今後他者に「こんなシーンがある」と伝える時は本当にそれが公式なのかどうかちゃんと調べた方がいいですよ😌 November 11, 2025
オーストラリアでもボッチ・ザ・ロックとヒロアカ観れるらしい アニメ観た事ないから観れへん.. ベビわる3とクラウドやってくれ! https://t.co/Gsk313aPct 🦉 November 11, 2025
https://t.co/zbsMv8uWvO
人口減少・少子高齢化・限界集落…課題も多い地方にDXは本当に浸透する?本気で地方創生を目指す企業の「覚悟」【NewsPicks/ダイワボウ情報システム/DISわぁるど/山形/AI/IT/地域/投資】
NewsPicks /ニューズピックス #AI要約 #AIまとめ
地方創生とDXで地方企業に未来はあるのか
🔳地方企業を取り巻く現状
人口減少と後継者不足により地方企業の倒産件数は増加しており、とくに北陸・九州・四国など地方圏の打撃が大きい。仕事がないというより、人手不足が原因で廃業に追い込まれるケースが多く、現状を放置するとビジネスの対象そのものが減っていく懸念が示されている。
🔳人手不足とIT・AIによる補完
地方では人が少ない一方で、都市部には人材が集中しているため、そのギャップをITとAIで埋める必要があると指摘。AIが人の代わりに一部業務を担いつつも、AIを支える人間のサポートが不可欠であり、その繋がりを設計しマッチングすることが自社の役割だと位置づけている。
🔳2025年の崖問題と後継者不在リスク
2025年の崖とは、古いシステムを作った担当者が退職や事故などで不在になり、システムがブラックボックス化して事業継続が困難になるリスクを指す。中小企業では「システムを1人で作った人」が抜けるだけで業務が止まる事例が多く、つなげる仕組みや「危ないですよ」と警告しながら再設計を提案するコンサル機能が重要とされている。
🔳崖を越える鍵はクラウド化
2025年の崖を乗り越えるには「クラウド化しかない」と明言。中小企業はデータを外に出すことに強い抵抗感があり、手元に置きたがるが、安全性や利便性を説明しながら「このデータから外に出しましょう」と段階的にクラウド移行を進めることが必要だと語られる。
🔳倭国発クラウドと倭国人のためのシステム
倭国初・倭国発のクラウドや、倭国人が倭国人のために作るシステムの必要性を強調。倭国企業同士で価格競争や消耗戦をするのではなく、共通プラットフォーム上で役割分担しながら全体の利益を高める方向へ進むべきだとし、自分たちがその「きっかけ役」にならなければならないと自覚している。
🔳DISワールドの役割と地方開催の意義
DISワールドは全国からIT企業が集まり、最新テクノロジーやソリューションを展示する大規模イベントで、山形のような地方で開催されること自体が貴重だと評価されている。イベント単体では赤字でも、ベンダー同士や来場者との交流・連携の場を提供し、新しい組み合わせやビジネスの種を生み出すことが本来の目的だと説明される。
🔳地方発DX事例の連鎖効果
新潟市のDISワールドを機に、長岡市長が教育への取り組みに共感し、共同でSTEAMラボを展開。翌年にはその事例が別のDISワールドで紹介され、福岡県飯塚市にもSTEAM教育が波及するなど、イベントを通じて自治体同士・地域同士のDXの輪が全国に広がる好例が紹介されている。
🔳地方IT企業のDX意欲と障壁
地方のIT企業やユーザー企業にはDXへの意欲がある一方で、「何から始めていいか分からない」「コスト」「人材不足」など複数の壁が存在する。IT人材は東京に流出し、地方IT企業への就職希望は少なく、人材確保が難しい現実が語られているが、農業などこれまでITが入り込んでこなかった分野にはむしろ大きなビジネスチャンスがあると見ている。
🔳サイバーセキュリティ意識のギャップ
地方においてセキュリティ意識は決してゼロではないが、他の課題との優先順位の中で後回しにされがちであり、経営層が必要性を認識していないケースも多い。近くで大きな被害が起きていないため危機感が薄く、セキュリティ対策が後手に回る構造が指摘され、展示会を通じて認知を広げる重要性が語られる。
🔳来場者が求めるものと地方開催の価値
来場者は最新情報や自社の効率化に役立つヒントを求めており、顧客対応や業務効率化につながる具体的なソリューションを探している。普段なら仙台や東京に行かないと得られない情報に、山形でアクセスできることへの感謝の声があり、地方開催が「情報格差の縮小」と「ビジネス加速」に役立っていることが示されている。
🔳DXの進捗と都市部とのマインド差
地方のDXは一歩一歩進んでいるが、都市部と比べるとスピードは遅めで、まだ抽象論の段階にある企業も多い。一方で自治体や企業で具体事例が増え始めており、クラウドなどを積極的に取り入れる企業も現れている。都市部ほど情報やサポート会社が多くない中で、イベントやパートナー企業が「気づきの場」として重要な役割を果たしている。
🔳中央集約よりも地域密着のメリット
ITサービスを中央に集約した方が効率的という見方に対し、地域にしかない情報やニーズ、現場に密着したサポートは地方拠点がなければ提供できないと反論。地域で顔の見える関係を築き、細かなサポートを行うことが、結果的に自社のビジネス拡大にもつながるという「社会貢献と事業成長の両立」モデルを志向している。
🔳地方創生は「儲け」より役割分担
地方ビジネス自体は拠点ごとに独立採算で十分やっていけるが、DISワールドのような大型イベントは短期的には赤字投資だと認めたうえで、それでも地方創生は役割分担だと強調。農業や特産品など、その地域にしかない強みをITで広く流通・発信し、「この商品なら世界で売れる」と後押ししていくことが地方創生への具体的な貢献になると語る。
🔳倭国人のアピール下手と文化継承への思い
地方には「こんなすごいものを作っているのに誰も知らない」隠れた資産が多いが、倭国人はアピールが極端に苦手だと指摘。萩の街で子どもから高齢者まで自然に挨拶を交わす文化に感動した体験から、地方に残る良い文化や価値観を倭国中に紹介したいという思いが地方創生への執着の根っこにあると語られる。
🔳IT企業としての使命と将来像
地方には人を置き、共に悩みながら課題を解決するのが自分たちの仕事であり、倭国企業同士が首を締め合うのではなく、同じプラットフォーム上で役割分担するべきだと主張。最終的には「ITの物流は倭国で一番給料が高い」と言える産業構造を作り、ITを通じて地方と都市、倭国全国をつなぐハブとして自社がきっかけになりたいというビジョンが語られている。
🔳DX浸透は道半ばだが前進している現実
地方にDXが浸透する未来はまだ先かもしれないが、イベントに集まる数千人の来場者や、具体的な事例の広がりは確かな前進を示している。ITで地域をつなぎ役割分担を進めることで、少しずつでも確実に地方創生へ近づこうとする人々の姿が、DISワールドとその周辺の取り組みを通じて浮かび上がっている。 November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。