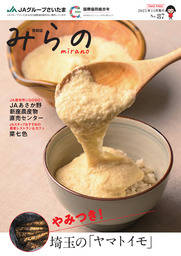農産物
0post
2025.11.27 16:00
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
💫途中経過のご報告💫
REDキャンペーンにご参加いただいた皆さん、ありがとうございます!まだ参加していない方は急いでフォロー&リポストと「知っているふくやまブランド農産物」をコメントしてくださ~い!!
#柿 #金時人参 が当たる!締切は11月30日(日)です😊
#ふくやまSUNプレゼント https://t.co/UUucyZP3lM November 11, 2025
1RP
「近いがうまい埼玉産」農産物フェア「さといも」「桂木ゆず」PR 埼玉県|JAcom 農業協同組合新聞 https://t.co/Rn8s1l2MoU https://t.co/hQy0OXApID November 11, 2025
1RP
国内産の最高級のもち米を使用
ササゲは現在では希少な豆を使用
河越米の玄米入り
黒米の持つ滋養強壮やアンチエイジングの効果は古くから認められ、重宝されてきた食材です。「足腰が疲れやすい」「身体の老化が気になる」という人におすすめです。
赤米に含有されているポリフェノール成分は、赤色色素成分のプロアントシアニジン類です。オリザ油化では、赤米の色のもとになっているこの色素成分に、高脂血症改善作用があることを見出しました。そのため、赤米エキスは脂質異常による生活習慣病の改善に高い効果が期待できる原料と考えられます。
雑穀お赤飯鬼切り3個で600円
配達の場合一日前にご予約お願いいたします。
℡ 0120-4153-87(よいこめやな)
お持ち帰りもできます。
祭日は休み
#川越
#河越米
#キッチンカー #小江戸市場カネヒロ
小江戸市場カネヒロの場所
https://t.co/jPharBYy3B
健康寿命延伸料理研究家
#雑穀エキスパート
#五ツ星お米マイスター
#農産物検査員
#お米の炊飯指導員
#小江戸市場カネヒロ November 11, 2025
第1回:フェアトレードはなぜ必要になったのか。背景にある搾取の歴史
チョコレートの箱に貼られた、あの青と緑のマーク。
あのマークが目に入ると、「今日の自分、なんか良いことした気がする」と思わせてくれる。フェアトレード認証は、そんな気持ちの良さとともに、すっかり私たちの生活の中に溶け込んだ。しかしだ。この認証をめぐる違和感は年々増している。
「本当に生産者のためになっているの?」
これらの疑問は、決して極端なものではない。むしろフェアトレードを理解するうえで避けて通れない歴史的背景が存在する。連載の第1回は、その歴史をいったん丁寧にほどいてみたい。
植民地時代は搾取が当たり前だった
コーヒー、カカオ、紅茶、綿花。これらの嗜好品や日用品は、18〜20世紀にかけて世界中の植民地で作られ、欧州に輸出されて莫大な富を生んだ。栽培したのは、現地の農民やプランテーション労働者。利益は、例外なく宗主国側に吸い上げられた。
植民地の支配構造はシンプルだ。軍隊が駐留し、現地の人々から土地と労働を取り上げ、単一作物を大量に作らせ、価格決定権は完全に欧州側が握る。この仕組みにフェアの要素は当然どこにもない。フェアトレードを理解するひとつの鍵は、そもそも搾取が標準設定だったという事実にある。
独立後も続いた見えない支配
「でも植民地は独立したじゃないか」そう思うかもしれない。たしかに20世紀後半、多くの国々は形式的には独立を果たした。しかし、カギとなるのは 経済の独立だった。宗主国が去った後の構造は、ゆるやかにこう変わっていく。
軍事支配から債務(借金)による支配へ
独立後、国家の基盤をつくるために多額の借金が必要になった国々。その借金を貸したのは誰か? 世界銀行、IMF、欧米の銀行・政府系機関。つまり旧宗主国の延長線上にある国際金融の網だ。
借金が返せない国は、「この作物をもっと輸出しなさい」「この政策をやりなさい」と条件を付けられる。これは軍隊ほど露骨ではないが、経済の意思決定を外部に握られるという意味で新しい支配だった。
資源メジャーが鉱物・石油を握る
金、銅、石油、ウラン。アフリカや中南米の主要資源は、多国籍企業(資源メジャー)が採掘権を握ることが多かった。支配の形は軍事ではなく、契約書に変わっただけだ。
農産物も価格決定権を握られたまま
コーヒーやカカオも同じ構図だ。先物市場は欧州と米国で動き、価格は彼らが事実上決める。生産者が価格に口を挟む余地はほぼゼロ。独立後も続く搾取のアップデート版だった。こうした長い歴史があるからこそ、20世紀末にフェアトレードが登場したとき、世界はある種の希望を見た。
フェアトレードは反省から生まれた
フェアトレード運動が生まれたのは1950〜60年代、ヨーロッパの教会系団体が中心だ。「植民地の歴史の尻ぬぐいをしよう」「生産者にもっと公平な価格を」という純粋な願いから始まった。その理想はまぎれもなく尊い。ただし問題は、運動が市場化した90年代以降に起きた。
認証制度が生まれた瞬間、力のバランスは欧州に戻った
フェアトレード認証は、誰が基準を作り、誰が監査し、誰が認証料を決め、誰が運営しているのか?この問いが非常に重要だ。現実として、主要な認証団体は欧州に本部を置き、基準作りも運営も欧州中心でスタートした。ここに構造的な矛盾が生じる。
生産者のための制度なのに、制度の主導権は再び欧州側が握ってしまった。これは意図的というより、歴史的経緯の積み重ねでそうなった部分もある。しかし結果として、欧州が作った規格を、南側の国々が従うという構図が出来上がった。植民地時代の命令が、現代では規格という形に姿を変えたとも言える。
認証ビジネス化したことで生まれた新たな疑問
フェアトレードの理念そのものは美しい。しかし認証制度となって市場に出ると、別の動きが生まれる。
認証料
監査料
ラベルの使用料
コンサルティング料
こうした費用の多くは、生産者ではなく認証側の国と組織に入っていく。もちろん健全に運営されている部分も多い。だが、制度が巨大になればなるほど、運営側の利害が生じるのは避けられない。ここで、フェアトレードは誰のための制度なのか?という根本的な問いが再び浮上する。
ではフェアトレードは必要なかったのか?
結論から言えば、フェアトレード運動が果たした役割は間違いなく大きい。生産者への意識、消費者教育、市場への問題提起、サプライチェーンの可視化、これらは、フェアトレードがなければ進まなかった。問題は制度が大きくなるほど、歪みも大きくなるという構造的な現象にある。
フェアトレードは、植民地時代から続いた搾取構造に挑んだ最初の大きな運動だった。しかしその制度が巨大な認証ビジネスへと成長したとき、歴史はもう一度、私たちに問いを投げかける。本当に生産者のためになっているのか?それとも、また別の形の支配構造が生まれてしまったのか?
第2回:支配のルールは変わらない独立後も続く新植民地主義
次回は、「独立後も続く新植民地主義」どうやって搾取はアップデートされたのかを掘り下げていく。
興味のある方はブログでお待ちします。
https://t.co/Fp6bQRbv20 November 11, 2025
皇紀2685年 令和7年2025/11/27
🇯🇵おはようございます😊🇯🇵
当面の間、韓国🇰🇷と中国🇨🇳に解決させるべき問題、かつ、倭国政府が要求すべき問題として啓蒙的活動を行っています。
よろしくお願いいたします✨🫡
🇰🇷韓国に解決させるべき問題🇰🇷
⚫︎デマによる補償要求撤回謝罪
半島出身労働者撤回
偽慰安婦撤回、虚偽少女像撤去
日立造船の供託金返還と不当判決取り消し謝罪
「福島汚染水」のデマ撤回と謝罪
韓国原発の多量トリチウムを認め、謝罪
竹島アシカ絶滅倭国責任のデマ撤回、謝罪
⚫︎侵略行為謝罪補償
竹島返還と倭国人殺傷財物強奪賠償
竹島周辺での軍事訓練の謝罪
李承晩ライン謝罪
レーダー照射謝罪
海神神社銅造如来立像観音寺観世音菩薩坐像窃盗謝罪
高麗版大般若経返還
これらの犯人引渡し
⚫︎北朝鮮情報技術漏洩
輸出管理制度確立運用
ホワイト国格下受容
⚫︎反日工作活動
倭国の議員への工作中止と謝罪
倭国の帰化議員の韓国撤収
旭日旗誹謗中傷謝罪
済州島観艦式自衛隊旭日旗不掲揚要求謝罪
軍艦島佐渡金山世界遺産登録妨害謝罪
NHK映像無許可使用賠償
反日虚偽歴史教育返上
福島県産品誹謗中傷
処理水放出妨害中止
倭国海名称詐称撤回
統一教会解散資産返納
世界各国への反日発信廃止・撤回
歴史教育等への干渉中止、謝罪
活動家粛清(誠信女子大学徐坰徳、尹美香議員)
倭国海への偽名撤回と謝罪
親日罪の廃止
在韓倭国大使館建替えの妨害中止、謝罪
動物園動物交換のレッサーパンダは受取り、カワウソは渡さない契約不履行の謝罪と実行
在日コリアン強制送還の引受け
アンミカを連れて帰れ
⚫︎デマ歴史拡散
天皇陛下侮辱発言謝罪
日王発言問題謝罪
安重根殺人犯賛美撤回
安重根記念館廃止、
大韓帝国要求による統合事実受入
靖国参拝黙れ
倭国統治の倭国語強制虚偽撤回
ハングル推奨事実受入
倭国統治の創氏改名強制虚偽撤回
朝鮮総督府爆破解体謝罪と復元
根拠のない起源主張の廃止及び謝罪
李舜臣の歴史的捏造の廃止
⚫︎倭国依存
通過スワップ停止
GSOMIA謝罪
日韓請求権協定遵守と発展尽力への感謝
果実種子等盗用
在日韓国人帰国
倭国海違法操業廃止
日韓トンネル廃止
海洋投棄廃棄物回収
技術や農産物種子苗木盗用の廃止・賠償
久石譲氏楽曲の無断使用賠償と謝罪
文化・技術のパクリ廃止、虚偽白状
🇨🇳倭国にいる中国人に関する問題🇨🇳
⚫︎ルールやマナーの悪さ
倭国のルールやマナーを理解せず、中国の悪い習慣を持ち込むことでトラブルが生じている。ゴミの放置、大きな声での会話、ルール無視。
⚫︎在日中国人の増加と社会への影響
在日中国人の人口増加により、倭国社会に「巨大な中国経済圏」が形成され、倭国の文化や社会構造が荒らされている。
⚫︎反日感情や犯罪増加
中国での反日教育の影響で倭国人を軽視し、反日的な行動が見られる。倭国での犯罪行為や、特定事件への関与がある。
⚫︎入国制限を求める
倭国社会への悪影響やトラブルへの懸念から、中国人の入国を制限すべき。 November 11, 2025
✨イベント報告✨
令和7年11月10日、JR小牛田駅,美里町農産物直売所「花野果市場」で「令和7年住宅用火災警報器普及啓発活動」を行ったヨ🐸
今回タオルやリーフレットのノベルティを配布し、多くの方に立ち止まってもらい、PR活動をすることができたヨ🎵
#住宅用火災警報器普及啓発活動
#大崎地域広域行政事務組合消防本部
#住警器
#とりカエル
#10年たったらとりカエル
https://t.co/2wfk69exWh November 11, 2025
第1回:フェアトレードはなぜ必要になったのか。背景にある搾取の歴史
チョコレートの箱に貼られた、あの青と緑のマーク。
あのマークが目に入ると、「今日の自分、なんか良いことした気がする」と思わせてくれる。フェアトレード認証は、そんな気持ちの良さとともに、すっかり私たちの生活の中に溶け込んだ。しかしだ。この認証をめぐる違和感は年々増している。
「本当に生産者のためになっているの?」
これらの疑問は、決して極端なものではない。むしろフェアトレードを理解するうえで避けて通れない歴史的背景が存在する。連載の第1回は、その歴史をいったん丁寧にほどいてみたい。
植民地時代は搾取が当たり前だった
コーヒー、カカオ、紅茶、綿花。これらの嗜好品や日用品は、18〜20世紀にかけて世界中の植民地で作られ、欧州に輸出されて莫大な富を生んだ。栽培したのは、現地の農民やプランテーション労働者。利益は、例外なく宗主国側に吸い上げられた。
植民地の支配構造はシンプルだ。軍隊が駐留し、現地の人々から土地と労働を取り上げ、単一作物を大量に作らせ、価格決定権は完全に欧州側が握る。この仕組みにフェアの要素は当然どこにもない。フェアトレードを理解するひとつの鍵は、そもそも搾取が標準設定だったという事実にある。
独立後も続いた見えない支配
「でも植民地は独立したじゃないか」そう思うかもしれない。たしかに20世紀後半、多くの国々は形式的には独立を果たした。しかし、カギとなるのは 経済の独立だった。宗主国が去った後の構造は、ゆるやかにこう変わっていく。
軍事支配から債務(借金)による支配へ
独立後、国家の基盤をつくるために多額の借金が必要になった国々。その借金を貸したのは誰か? 世界銀行、IMF、欧米の銀行・政府系機関。つまり旧宗主国の延長線上にある国際金融の網だ。
借金が返せない国は、「この作物をもっと輸出しなさい」「この政策をやりなさい」と条件を付けられる。これは軍隊ほど露骨ではないが、経済の意思決定を外部に握られるという意味で新しい支配だった。
資源メジャーが鉱物・石油を握る
金、銅、石油、ウラン。アフリカや中南米の主要資源は、多国籍企業(資源メジャー)が採掘権を握ることが多かった。支配の形は軍事ではなく、契約書に変わっただけだ。
農産物も価格決定権を握られたまま
コーヒーやカカオも同じ構図だ。先物市場は欧州と米国で動き、価格は彼らが事実上決める。生産者が価格に口を挟む余地はほぼゼロ。独立後も続く搾取のアップデート版だった。こうした長い歴史があるからこそ、20世紀末にフェアトレードが登場したとき、世界はある種の希望を見た。
フェアトレードは反省から生まれた
フェアトレード運動が生まれたのは1950〜60年代、ヨーロッパの教会系団体が中心だ。「植民地の歴史の尻ぬぐいをしよう」「生産者にもっと公平な価格を」という純粋な願いから始まった。その理想はまぎれもなく尊い。ただし問題は、運動が市場化した90年代以降に起きた。
認証制度が生まれた瞬間、力のバランスは欧州に戻った
フェアトレード認証は、誰が基準を作り、誰が監査し、誰が認証料を決め、誰が運営しているのか?この問いが非常に重要だ。現実として、主要な認証団体は欧州に本部を置き、基準作りも運営も欧州中心でスタートした。ここに構造的な矛盾が生じる。
生産者のための制度なのに、制度の主導権は再び欧州側が握ってしまった。これは意図的というより、歴史的経緯の積み重ねでそうなった部分もある。しかし結果として、欧州が作った規格を、南側の国々が従うという構図が出来上がった。植民地時代の命令が、現代では規格という形に姿を変えたとも言える。
認証ビジネス化したことで生まれた新たな疑問
フェアトレードの理念そのものは美しい。しかし認証制度となって市場に出ると、別の動きが生まれる。
認証料
監査料
ラベルの使用料
コンサルティング料
こうした費用の多くは、生産者ではなく認証側の国と組織に入っていく。もちろん健全に運営されている部分も多い。だが、制度が巨大になればなるほど、運営側の利害が生じるのは避けられない。ここで、フェアトレードは誰のための制度なのか?という根本的な問いが再び浮上する。
ではフェアトレードは必要なかったのか?
結論から言えば、フェアトレード運動が果たした役割は間違いなく大きい。生産者への意識、消費者教育、市場への問題提起、サプライチェーンの可視化、これらは、フェアトレードがなければ進まなかった。問題は制度が大きくなるほど、歪みも大きくなるという構造的な現象にある。
フェアトレードは、植民地時代から続いた搾取構造に挑んだ最初の大きな運動だった。しかしその制度が巨大な認証ビジネスへと成長したとき、歴史はもう一度、私たちに問いを投げかける。本当に生産者のためになっているのか?それとも、また別の形の支配構造が生まれてしまったのか?
第2回:支配のルールは変わらない独立後も続く新植民地主義
次回は、「独立後も続く新植民地主義」どうやって搾取はアップデートされたのかを掘り下げていく。 November 11, 2025
第1回:フェアトレードはなぜ必要になったのか。背景にある搾取の歴史
チョコレートの箱に貼られた、あの青と緑のマーク。
あのマークが目に入ると、「今日の自分、なんか良いことした気がする」と思わせてくれる。フェアトレード認証は、そんな気持ちの良さとともに、すっかり私たちの生活の中に溶け込んだ。しかしだ。この認証をめぐる違和感は年々増している。
「本当に生産者のためになっているの?」
これらの疑問は、決して極端なものではない。むしろフェアトレードを理解するうえで避けて通れない歴史的背景が存在する。連載の第1回は、その歴史をいったん丁寧にほどいてみたい。
植民地時代は搾取が当たり前だった
コーヒー、カカオ、紅茶、綿花。これらの嗜好品や日用品は、18〜20世紀にかけて世界中の植民地で作られ、欧州に輸出されて莫大な富を生んだ。栽培したのは、現地の農民やプランテーション労働者。利益は、例外なく宗主国側に吸い上げられた。
植民地の支配構造はシンプルだ。
軍隊が駐留し、
現地の人々から土地と労働を取り上げ、
単一作物を大量に作らせ、
価格決定権は完全に欧州側が握る。
この仕組みにフェアの要素は当然どこにもない。フェアトレードを理解するひとつの鍵は、そもそも搾取が標準設定だったという事実にある。
独立後も続いた見えない支配
「でも植民地は独立したじゃないか」そう思うかもしれない。たしかに20世紀後半、多くの国々は形式的には独立を果たした。しかし、カギとなるのは 経済の独立だった。宗主国が去った後の構造は、ゆるやかにこう変わっていく。
軍事支配から債務(借金)による支配へ
独立後、国家の基盤をつくるために多額の借金が必要になった国々。その借金を貸したのは誰か? 世界銀行、IMF、欧米の銀行・政府系機関。つまり旧宗主国の延長線上にある国際金融の網だ。
借金が返せない国は、「この作物をもっと輸出しなさい」「この政策をやりなさい」と条件を付けられる。これは軍隊ほど露骨ではないが、経済の意思決定を外部に握られるという意味で新しい支配だった。
資源メジャーが鉱物・石油を握る
金、銅、石油、ウラン。アフリカや中南米の主要資源は、多国籍企業(資源メジャー)が採掘権を握ることが多かった。支配の形は軍事ではなく、契約書に変わっただけだ。
農産物も価格決定権を握られたまま
コーヒーやカカオも同じ構図だ。先物市場は欧州と米国で動き、価格は彼らが事実上決める。生産者が価格に口を挟む余地はほぼゼロ。独立後も続く搾取のアップデート版だった。こうした長い歴史があるからこそ、20世紀末にフェアトレードが登場したとき、世界はある種の希望を見た。
フェアトレードは反省から生まれた
フェアトレード運動が生まれたのは1950〜60年代、ヨーロッパの教会系団体が中心だ。「植民地の歴史の尻ぬぐいをしよう」「生産者にもっと公平な価格を」という純粋な願いから始まった。その理想はまぎれもなく尊い。ただし問題は、運動が市場化した90年代以降に起きた。
認証制度が生まれた瞬間、力のバランスは欧州に戻った
フェアトレード認証は、誰が基準を作り、誰が監査し、誰が認証料を決め、誰が運営しているのか?この問いが非常に重要だ。現実として、主要な認証団体は欧州に本部を置き、基準作りも運営も欧州中心でスタートした。ここに構造的な矛盾が生じる。
生産者のための制度なのに、制度の主導権は再び欧州側が握ってしまった。これは意図的というより、歴史的経緯の積み重ねでそうなった部分もある。しかし結果として、欧州が作った規格を、南側の国々が従うという構図が出来上がった。植民地時代の命令が、現代では規格という形に姿を変えたとも言える。
認証ビジネス化したことで生まれた新たな疑問
フェアトレードの理念そのものは美しい。しかし認証制度となって市場に出ると、別の動きが生まれる。
認証料
監査料
ラベルの使用料
コンサルティング料
こうした費用の多くは、生産者ではなく認証側の国と組織に入っていく。もちろん健全に運営されている部分も多い。だが、制度が巨大になればなるほど、運営側の利害が生じるのは避けられない。ここで、フェアトレードは誰のための制度なのか?という根本的な問いが再び浮上する。
ではフェアトレードは必要なかったのか?
結論から言えば、フェアトレード運動が果たした役割は間違いなく大きい。生産者への意識、消費者教育、市場への問題提起、サプライチェーンの可視化、これらは、フェアトレードがなければ進まなかった。問題は制度が大きくなるほど、歪みも大きくなるという構造的な現象にある。
フェアトレードは、植民地時代から続いた搾取構造に挑んだ最初の大きな運動だった。しかしその制度が巨大な認証ビジネスへと成長したとき、歴史はもう一度、私たちに問いを投げかける。本当に生産者のためになっているのか?それとも、また別の形の支配構造が生まれてしまったのか?
第2回:支配のルールは変わらない独立後も続く新植民地主義
次回は、「独立後も続く新植民地主義」どうやって搾取はアップデートされたのかを掘り下げていく。 November 11, 2025
「ビジネス」要素も重要。「この電話は貿易に関するものだったと述べ、米国が中国の大豆購入の実行遅れに懸念を抱いていると説明した。トランプは火曜夜、習に対して「もっと早く買ってほしい」と伝えたと述べた。中国が米農産物の購入を約束していることに関してだ」 November 11, 2025
トランプ氏、中国の習主席は米国産農産物の購入拡大に大筋合意
・習氏は「良い意味でとても驚かせると思う」-トランプ氏
・高市氏とは「素晴らしい」会談を行った-大統領専用機内で発言
👉大豆など米国農産物購入を重視し、中間選挙モードが鮮明に
https://t.co/cLfP5rssGn November 11, 2025
あの値段で全国で買えてさ農産物である紅茶の味を一定に保つって大変だと思うんだよ。企業努力ありがたい。しかも万人受けする味で美味しくてロングセラー。職場ではあまり茶への偏愛を出してないから"紅茶はみんな美味しい!"でまとめちゃったけど、日東さんへの愛的には捲し立てるべきだったかなと。 https://t.co/ng1PupOAL6 November 11, 2025
第18回 志木市民まつりが開催されます!!
https://t.co/1ICEyxUDLM
カパル・カッピーはもちろんスペシャルゲストのジャビットくんなど参加の「ご当地キャラクター大集合」やグッズ販売、第7回ご当地グルメ王決定戦、農産物品評会、消費生活展、フリーマーケットや長野県飯綱町のりんご販売など楽しいイベントが盛りだくさんの志木市民まつりが今年も開催されます!!
場所はいろは親水公園および志木市役所です
東武東上線志木駅東口からバスで約5分
(東武バスまたは国際興業バスで、志木市役所前または志木市役所で下車)
皆さまぜひご来場ください!!
#志木市 #東武東上線 #志木市民まつり #カパル #カッピー #キャラクター #ゆるキャラ November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。